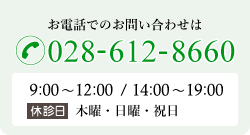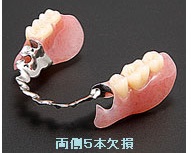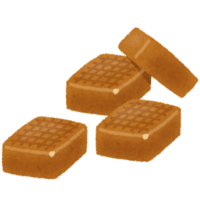宇都宮市兵庫塚町の歯医者 歯周病専門医の山之内です。
歯肉退縮と生活の質について書いていきたいと思います。
歯肉退縮とは、歯の周りの組織がすり減り、歯の根っこが露出した状態のことをいいます。
歯肉が退縮すると、歯ぐきと歯の間にすきまができ、お口の問題の原因となる虫歯菌や歯周病菌などの細菌に感染しやすくなります。

治療しないまま放置すると、歯の周りの組織と骨構造が損傷して、歯を失いかねません。
歯肉退縮は多くの人に起こっているお口の病気です。徐々に進行するので、ほとんどの人は歯ぐきの退縮が起こっていることに気づきません。
2016年3月に『Community Dent Oral Epidemiology』で発表されました。
「ブラジルにおける歯肉退縮とQOL(生活の質)の関係性」に関する論文を紹介します。
この論文では、歯肉退縮とQOLの関連性について、ブラジル人の成人を対象に調査を実施しました。
被験者は、6本以上の歯を有する35~59歳の男女740人で構成されています。
歯肉退縮は全ての残存歯に対し4か所ずつ測定し、
口腔内のQOLを測定するためにThe Oral Health Impact Profile(OHIP:QOLの尺度を測る基準の1つ)を使用し、
OHIPによる測定は、知覚過敏・年齢・性別・社会的・経済的ステータス・喫煙、口腔ケア状態・歯牙の喪失などにより結果が異なります。
一本以上の歯に2~5mm以上の歯肉退縮があることは、OHIPによる測定結果に大きく影響し、QOLを低下させることがわかりました。
一本以上の歯に2㎜以上の歯肉退縮がある場合、歯肉退縮がない場合と比べて約2倍以上QOLを低下させることがわかっ
部位別に測定した際、頬側近心を測定した結果、前歯部の歯肉退縮はQOLを低下しますが、
臼歯部の歯肉退縮はQOLに影響を及ぼさないことがわかりました。
下顎における歯肉退縮は、QOLに影響を受けませんでした。
4㎜以上の歯肉退縮によって、歯の機能的な限界、物理的な痛み、物理的な不快感、情緒不安定などの症状が見られました。
知覚過敏単独症状ではQOLに影響はありませんが、
主に頬側の歯肉退縮と同時に起きた場合にはQOLの低下に影響を及ぼすことがわかりました。
結論として、QOLの低下は主に歯肉退縮が上顎前歯部に現れるときに認められました。
日本人の顎の骨の特徴として、骨も歯肉も薄い傾向があります。
そのため、歯周病が進行すると歯肉が下がりやすい傾向になりやすいと言えますね。
より良い生活の質を得るためには、お口の健康も考慮に入れたほうがいいですね。
そのためには、歯周病が進行しないように定期的なメインテナンスが必要で
悪くしないよう予防していきましょう。
歯肉退縮は、歯茎が後退することで歯根が露出し、歯肉の炎症や歯根の感染、歯の不安定性などを引き起こす歯周病の一種です。
歯肉退縮が進行すると、歯の感覚過敏や歯の黄ばみなどの美容上の問題が生じるだけでなく、歯垢や食物の詰まりが増えて口臭や口内炎の原因となります。
歯肉退縮は、口腔内の健康状態だけでなく、QOL(生活の質)にも影響を与える可能性があります。
例えば、歯肉退縮が進行すると、歯の感覚過敏が増し、冷たい飲み物やアイスクリーム、熱い飲み物や食べ物などを摂取することが困難になることがあります。
また、歯茎の痛みや腫れ、口内炎などの症状が現れることもあります。
さらに、歯肉退縮が進行すると、歯の根の露出が進んで歯の支持力が弱くなり、歯が抜け落ちる可能性が高くなります。
このため、噛む力が弱まり、食べ物の摂取が困難になったり、摂取量が減少することで、栄養不足や健康悪化のリスクが高まることもあります。
歯肉退縮の治療には、歯周病治療、歯肉移植、インプラント治療などがあります。
早期に治療を受けることで、QOLの低下や健康リスクを回避することができます。
歯肉退縮に対する治療が気になる方は、下記をクリックしてください。