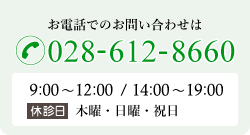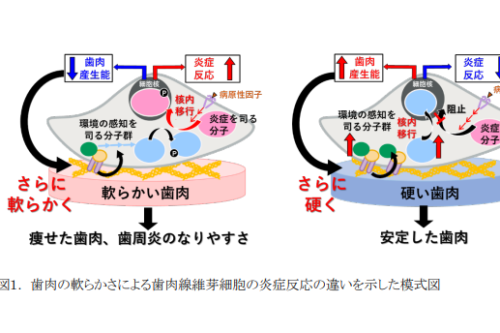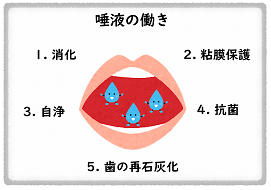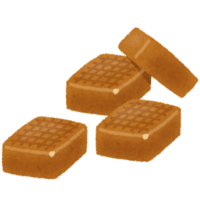宇都宮市兵庫塚町の歯医者 やまのうち歯科医院の山之内です。
今回は、虫歯の感染について書いていきます。
ステプトコッカス・ミュータンスは、口腔内に自然に存在する細菌の一種であり、糖分を代謝して酸を生成します。
虫歯のプロセスは以下のように進行します。
まず、口腔内の糖分を含む食品や飲み物を摂取すると、ステプトコッカス・ミュータンスなどの口腔内の細菌がこれらの糖分を利用して代謝します。
この代謝過程により、細菌は酸を生成します。
生成された酸は歯のエナメル質を溶かし、歯の表面に穴(虫歯)を作ることがあります。
さらに、酸によって歯の表面が脱灰されると、他の細菌や食べかすが歯の表面に付着しやすくなり、虫歯の進行が加速されます。
なお、虫歯の発生には他の細菌も関与している場合がありますが、ステプトコッカス・ミュータンスが最も一般的で重要な原因菌とされています。
したがって、虫歯予防のためには、口腔衛生の習慣や糖分の摂取量の管理など、ステプトコッカス・ミュータンスの増殖を制御することが重要です。
昨今虫歯の原因菌について言われていることはありますが、子供の虫歯のリスクを高くする菌はミュータンス菌と思われます。
また、一口にミュータンス菌といっても、実はいろいろなタイプがあり、グループ分けもされています。
母子を対象にした研究で、多くの親とその子から性状が同じミュータンス菌が検出されました。
という複数の報告が1970年代からされており、2000年以降も含め、性状だけでなく遺伝子の解析など、多方面から検討がなされました。
そして、親と子では共通のミュータンス菌がいる、すなわち親から子にうつっていることを示す研究結果が積み上げられてきました。
さらに、これら多くの論文を系統的にまとめて再解析した論文においても、子の世話をする人から子への、特に母親が主に世話をする場合は、母から子へのミュータンス菌の伝播には科学的根拠があると結論づけられると述べられています。
以上により、ミュータンス菌が親から子にうつることは、科学的な根拠をもっていわれていることなのです。
しかしながら、乳幼児期のスキンシップの重要性はわかっており、この狭間で悩む人も多いのではないでしょうか?
では、虫歯菌に感染するからと、乳幼児期に口移しで食べたり、キスをしたりすることは避けた方がいいのでしょうか?
虫歯菌の感染が問題なら、口腔ケアを念入りにすればいい話で、口移しも含めてスキンシップを制限する必要はないと思われます。
実際、虫歯菌が移ったとしても虫歯菌が増える環境でなければ悪化はしません。
食生活や飲食物によって変わってくるといわれています。
それでなくともスキンシップが禁じられてしまうパンデミックな状態で、スキンシップ欠如の子供への影響の方が深刻に思われます。
ハーバード大学心理学科は、1歳半ぐらいの幼児は唾液の交換を伴う行動を見て、社会性を判断していることを示した研究でサイエンスに掲載されている文献があります。
それ以外の菌についての原因菌は、ラクトバチラス菌といわれは食物に含まれており、炭水化物や砂糖、乳酸菌飲料などに多く含まれています。
ラクトバチルス菌は腸内にいると身体に良い働きをする善玉菌ですが、お口の中ではミュータンス菌によって作られた虫歯に定着して虫歯をどんどん進行させる働きをします。
虫歯の穴や、被せ物、詰め物と歯の隙間などを好み、それらの部分に付着して棲み着いてしまいます。
そのため、虫歯の穴を大きくしたり、詰め物や被せ物と歯の間に虫歯を作るといわれています。
幼児期での親密性の概念:幼児期に唾液の共有を人間同士の親密さを判断するのにしようしているというタイトルです。
この研究は、他人の唾液が混じるのをいとわない行為は、人間同士の親密な関係を示すとのことです。
唾液が混じるという行為は、親密でないと行わない行為ですから、大人だけでなく子供もわかるということなのですね。
同じストローでジュースを飲んでいる子供と、別々に分けて食べている男女の子供を見て、唾液が混じっても同じストローでジュースを飲んでいる子供の方がより兄妹である可能性が高いと感じるとのことです。
1歳半の幼児のみならず、8ヶ月の乳児でも、唾液を共有していることを感知し、それを親密なサインとして理解しているとのことです。
他にも様々な確認実験を行い、人はかなり早い段階から社会的親密度を判断でき、その基準として唾液共有が行える仲かどうかで判断しているということです。
いずれにせよ、唾液共有をいとわない関係を積極的に作らないと、子供に親密とは思ってもらえないことを示した論文です。
虫歯菌が感染するからという理由で、お子さんとのスキンシップを避けるということはしないほうがいいとのことですね。
ただし、スキンシップをする前に虫歯や歯周病の治療を行い、虫歯菌や歯周病菌を少なくしたうえでスキンシップをしましょう。
虫歯と呼ばれる原因菌のほとんどは、ステプトコッカス・ミュータンスがほとんどで、その他の関連する菌もありますが子供のうちはこの菌がメインで活動すると思っていいと思います。
予防方法は、菌を少なくする方法ですから歯ブラシとフロス、フッ素を行うことが重要になりますね。



子供の虫歯の放置について気になる方は下記をクリックしてください。
子供のむし歯の放置